激しい降りではないが、ときどき雨が降る一日だった。ゆすらうめを収穫。今までで一番たくさんとれた。なぜか鳥が来ないのが不思議。
ダライ・ラマ14世が「ダライ・ラマの転生制度は続く」と発言したとネットニュース。10年とかもっと前かもしれないが、転生制度(というかシステムというか)は自分の代で終わりにすると言われていたと思うのだが、考えが変わったということなんだろうか、詳細は不明。
チベットの活仏は転生する、らしい、そういうことになっている。活仏が亡くなると高僧たちが占いをして、大体の方角が決まり、転生した子供を探しに行く。条件に合う複数の子どもが集められ、その中で最も転生前の記憶を残している者が選ばれる。つまり亡くなってすぐではなく、少なくとも数年の時間がかけられる。今の14世は13世の持ち物を「僕のものだ」と言ったんじゃなかったかな……。集められた子の中で最も聡明な子(その場の空気を感じ取り自分のすべきことを理解できる)を選ぶ、ということだと私は理解しているが。もちろん健康も大事な要素だろうし。
14世が世を去る日はいつか来るわけで、その時にはかなり混乱するのだろうと思う。転生者が自治区外で見つかるシナリオにするしかないと思うが、さてどうなるのだろう。
補足* 活仏だけではなくチベット仏教ではすべてのものは輪廻転生する。だから30年40年前まではチベット人は来世もまた人に生まれるようにと祈っていたと聞いている。現代はわからない(現世利益の追求にも向かっているかも)。
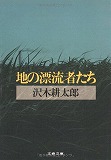 『地の漂流者たち』 沢木耕太郎
『地の漂流者たち』 沢木耕太郎
著者の最も初期に書かれたルポルタージュが6編。1970年代初頭のものばかり。ザ・70年代であり、ザ・団塊の青春時代。文体は硬いけれども50年後の今読んでも面白い。川崎が若者の街だったとか、その頃の若者たちも今と変わらずさっさと転職しては雇い主を嘆かせていたのだとか、そういうことが面白かった。
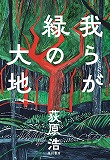 『我らが緑の大地』 萩原浩
『我らが緑の大地』 萩原浩
植物には知能があり、自分たちの間での伝達機能も持っている。地球上の有機体の重さで言うと植物が99.7%を占めるのだそうだ。そんな植物たちが人間の横暴に怒り、地球を取り戻すべく蜂起する……、そういう話だった。
蘊蓄的なものはそれなりに面白かったが、小説としてはぐだぐだでリアリティにも迫力にも欠け、ホラーなのにまるで怖くないっていう……(-_-;) 緊迫した場面でも主人公とその3歳の子どもの間が抜けた会話やら、主人公の「ワタシがんばる」的独白が続いてうんざりする。
☆2 面白さがわからなかった
何かこの感じ、記憶にあるなと思ったら3年ほど前に別の小説を読んでいた。それは昆虫パニックホラーだった(^^; 緊迫感のなさがこの人の作風なんだろう。B級っぽさがすごい。
ではまた
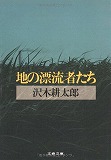 『地の漂流者たち』 沢木耕太郎
『地の漂流者たち』 沢木耕太郎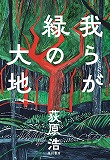 『我らが緑の大地』 萩原浩
『我らが緑の大地』 萩原浩