今日の最高気温は17.7℃とか。涼しい通り越してもはや寒いです。
極端な気温には困る。
寒暖差アレルギーなのか秋のイネ科なのか、風邪ではないけどくしゃみばかりしています。掃除してないせいもある(^^;
午前中に町の役場と、小諸市まで行って年金事務所。
役場では保険証は返せたんだけど、4枚も記入項目が多い書類を渡され、現場で書ける気がしなくて持ち帰りになる。書けるけど、後でもいいかと思った。
年金事務所は戸籍抄本を忘れて突撃してしまい、あらためて必要書類などが書かれた紙を受け取り、来週の予約をして帰って来た。旅のことなんかは鬼のように検索しまくるくせに、こういうことは「現場に行けば何とかなるだろう」「現場に行くのが一番確実」と思ってしまうのが悪い癖だと思う。
まぁ、年金事務所は他にも書くべき書類があって渡されたし、どのみち1回では済まなかった(もちろん準備万端整えたら1回でいけます)ということで気を取り直したいと思う。
あとは持ち帰った遺品の整理をぼちぼちとやっている。
時間がない人の場合は、もちろん全部そのまま処分してしまうというのもありだと思うし、それでいいと思う。
でも時間の余裕がある私の場合、色々なものを仕分けながら整理していく時間もまた、必要なのではないかと思う。父が書いたものや、母が書いたもの、メモや手帳、1枚か2枚書きかけただけのノート、どこにでも潜んでいる不織布マスク、驚くほど小さく切り揃えられて小さな袋に入っている紙片、そしてありとあらゆる種々雑多なモノたち……。見なくてもいいし、見ない方がいいものももちろんあるが、これはこれで無駄な時間ではないように思う。
*

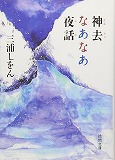 『神去なあなあ日常』『神去なあなあ夜話』
『神去なあなあ日常』『神去なあなあ夜話』
三浦しをん著。
横浜で暮らしていた青年が高校卒業と同時に親と教師に騙されて三重県の山深い村に飛ばされ、林業に従事し村の人々に受け入れられ愛され、村人の一員として立派に成長していく、というお話だった。一種のビルドゥングスロマンで合っているか? 私も自分が住んでいる土地の森を開墾したことがあるので、木を伐る場面などはとても面白く懐かしく読んだ。そういえば私には、木から木へ渡りながらスギの枝打ちができる友人がいたっけな(今はトドみたいになっちゃって想像もできないのだが)。
☆4 現代のおとぎ話、それにしても「みんなたち」って何だよ!
作中、たびたび出てくる「みんなたち」という言葉が引っかかった。これはこの青年がパソコンでひそかに村での日々を綴っているという設定の小説で、青年はいないはずの読者に向かって呼びかけたり話しかけたりする。その時に「みんなたち、元気?」みたいな感じで。
いや、三浦しをんさんは手練れの書き手だから、間違っているはずはないんだけど、見慣れないもので……。
ではまた